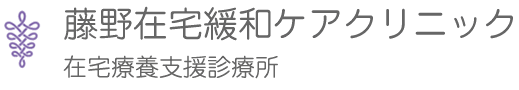畏怖の心
世の中には自分ではどうしようもないことが多々あります。ブッダが四苦と話された「生老病死」も、基本的には自分ではどうしようもないことなのだろうと感じます。アンチエイジングという言葉がありますが、老いや死に抗うことができないことは異論のない所だと思います。そして病についても同じように感じることがあります。
当然、治すことができる病はたくさんありますが、医療の関与よりもその人自身の治癒力が主体となっていることが多いことも事実です(もちろん救急疾患や急性期の病態では西洋医学が果たす役割は非常に大きく医療を否定するものではありませんので誤解されないでください。)。
話が逸れましたが、治せる病であればその努力を行っていくことはとても大切なことでしょう。でも治せない病であればどのように医療と付き合っていくか、徐々にその視点を変えていく必要があるのかもしれません。この、人間の力で変えられる事と変えられない事をどのように見極めていくか、その境は白黒きれいに分けられるわけではないので常に悩む問題です。
例えばがんを担っている方が化学療法(抗がん剤治療)をいつまで続けるかという問題があります。製薬会社の努力によって数多くの抗がん剤が開発され、ある抗がん剤の効果がなくなっても次の抗がん剤が用意されている時代となりました。抗がん剤という言葉は「がんに抗(あらが)う薬」と書きますが、小児がん、血液がんの一部を除きその効果は限定されたものです。どこまで抗がん剤を続ければ利益が大きいのか。どこで抗がん剤をやめた方がよいのか。
医師は画像所見や血液データにその判断基準の多くを求めます。そのため実際には生活が十分に送れなくなっているにも関わらず化学療法(抗がん剤治療)が続けられている場合もあります。
人の力ではどうすることもできないことがあることを受け止めつつ、データに左右されすぎずに実際の生活実感を大切に自らが判断していくことも必要なのかもしれません。
その判断のためには畏怖の心が求められているのかもしれません。